
※本記事はPRを含みます
北海道の地震・雪害・火山と冬季停電対策
この記事では、北海道特有の自然災害リスクと、特に冬季に深刻な影響をもたらす大規模停電への具体的な備えについて、初心者にも分かりやすく解説します。
北海道は、広大な大地と豊かな自然に恵まれる一方で、多様な自然災害と隣り合わせの地域です。過去には2018年の北海道胆振東部地震のような大規模な地震に見舞われ、全道が長期間の停電、いわゆるブラックアウトを経験しました。また、毎年のように豪雪や吹雪といった雪害が発生し、交通網の麻痺や孤立集落の問題を引き起こしています。さらに、有珠山や樽前山、十勝岳など多くの活火山を抱えており、噴火のリスクも常に存在します。これらの災害は、特に厳しい寒さに見舞われる冬季において、停電や交通寸断と結びつくことで、私たちの生活により深刻な影響を及ぼしかねません。「北海道で冬の停電にどう備えるべきか」「家庭でできる具体的な地震対策は何か」「雪害や火山噴火に対してどのような準備が必要か」といった道民の皆様が抱える疑問や不安に答えるため、本記事では具体的な防災グッズのリストや備蓄方法、災害発生時の情報収集のポイントまで、いざという時に本当に役立つ情報を網羅的にお伝えします。
北海道の多様な自然災害リスクとは
北海道が抱える地震、雪害、火山という主要な自然災害の概要と、過去の事例から学ぶべき教訓を解説します。
北海道は、その地理的特性から、地震、雪害、火山噴火という多様な自然災害のリスクに常にさらされています。これらの災害は単独で発生するだけでなく、時には複合的に絡み合い、被害を拡大させることもあります。それぞれの災害の特性を理解し、適切な備えをすることが、道民一人ひとりの生命と財産を守る上で非常に重要です。
教訓:北海道胆振東部地震の影響
2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震は、最大震度7を観測し、道内全域に甚大な被害をもたらしました。特に深刻だったのは、大規模な土砂災害と、国内初となるブラックアウト(全域停電)です。この地震により、道内のほぼ全ての火力発電所が停止し、約295万戸が停電しました。停電は数日間に及び、都市機能の麻痺、情報通信の途絶、医療機関の機能低下、食料品や燃料の供給不足など、道民生活に広範な影響が出ました。また、厚真町などでは大規模な土砂崩れが発生し、多くの尊い命が失われました。この経験から、私たちは大規模地震への備えはもちろんのこと、長期間の停電に対する具体的な対策の必要性を痛感させられました。例えば、電源に依存しない暖房器具や調理器具の確保、十分な量の食料・水・医薬品の備蓄、そして正確な情報を得るためのラジオやモバイルバッテリーの準備などが、その後の防災意識の中で強く認識されるようになりました。
冬季に頻発する雪害とその被害
北海道の冬は厳しく、毎年のように大雪や吹雪による雪害が発生します。雪害は多岐にわたり、交通機関の麻痺による物流の遅延や生活物資の不足、視界不良による交通事故の多発、屋根からの落雪や雪下ろし中の事故、水道管の凍結・破裂による断水などが挙げられます。特に、数日間にわたり集落が孤立するケースもあり、高齢者や支援が必要な方々にとっては命に関わる事態となり得ます。2022年から2023年にかけての冬も、道内各地で記録的な大雪に見舞われ、長期間の通行止めや公共交通機関の運休が相次ぎました。雪害への備えとしては、除雪用具の準備や食料・燃料の備蓄はもちろんのこと、気象情報をこまめに確認し、不要不急の外出を控える判断も重要です。また、車で外出する際には、立ち往生に備えて防寒具、スコップ、毛布、非常食などを必ず携行する必要があります。
活火山の現状と噴火時の備え
北海道には、有珠山、樽前山、十勝岳、雌阿寒岳、北海道駒ヶ岳など、気象庁が常時観測している活火山が多数存在します。これらの火山は過去に何度も噴火を繰り返しており、今後も噴火する可能性があります。火山噴火が発生すると、大きな噴石や火砕流、火山泥流といった直接的な被害に加え、広範囲に火山灰が降ることによる健康被害や農作物への被害、交通機関の混乱、精密機械の故障などが懸念されます。例えば、有珠山は2000年にも噴火し、周辺住民は長期間の避難生活を余儀なくされました。火山への備えとしては、まず居住地域や勤務先の近くにある活火山の情報を把握し、ハザードマップで危険箇所や避難経路を確認しておくことが基本です。気象庁が発表する噴火警戒レベルに注意し、レベルが引き上げられた場合には、行政の指示に従い速やかに避難行動をとる必要があります。また、降灰に備えて防塵マスクやゴーグル、雨具などを準備しておくことも大切です。
大地震への備えと具体的な対策
大規模な地震が発生した際に取るべき行動と、事前に家庭で準備しておくべき安全対策について具体的に説明します。
いつ発生するかわからない大地震に備えるためには、日頃からの準備が何よりも重要です。家庭内での安全対策を徹底し、いざという時の行動手順を家族で話し合っておくことで、被害を最小限に抑えることができます。
家庭内の安全確保と避難計画
まず、家庭内での安全確保策として、家具の転倒・落下・移動防止対策が不可欠です。特に寝室や子供部屋では、タンスや本棚、テレビなどが倒れてこないよう、L字金具や突っ張り棒などで壁や天井にしっかりと固定しましょう。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ることで、割れたガラスによる怪我を防ぐことができます。また、食器棚や吊り戸棚には、扉が開かないように耐震ラッチを取り付けると効果的です。懐中電灯やスリッパなどを枕元に常備しておくことも、夜間の地震発生時に役立ちます。
次に、非常持ち出し袋の準備です。中には飲料水、非常食(カンパン、アルファ米、缶詰など)、携帯トイレ、救急セット、常備薬、懐中電灯、ラジオ、電池、マスク、軍手、下着、タオル、貴重品(現金、身分証明書のコピーなど)などを入れ、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。少なくとも3日分、できれば1週間分の備蓄が推奨されています。食料や水はローリングストック法を活用し、普段の生活で消費しながら買い足していくことで、期限切れを防ぎ、常に新しいものを備蓄できます。
そして、家族で避難場所と避難経路を確認し、実際に歩いてみることが重要です。災害時にはぐれた場合の連絡方法(災害用伝言ダイヤル171やSNSの安否確認機能など)も事前に決めておきましょう。地域のハザードマップを入手し、自宅周辺の危険箇所(崖崩れ、浸水エリアなど)を把握しておくことも大切です。
地震発生!その時の行動手順
実際に大きな揺れを感じたら、まずは落ち着いて身の安全を確保することが最優先です。丈夫なテーブルや机の下に隠れるか、物が落ちてこない、倒れてこない場所に移動し、頭を保護しましょう。慌てて外に飛び出すのは危険です。揺れが収まったら、まず火の元の確認と初期消火を試みます。ガス漏れの危険がある場合は、元栓を閉め、窓を開けて換気し、絶対に火気を使用しないでください。ブレーカーも落としておくと、通電火災の予防になります。
次に、ドアや窓を開けて避難経路を確保します。特にマンションなどでは、建物が歪んでドアが開かなくなることがあります。家族や近隣の人々の安否を確認し、協力して救助や避難誘導にあたりましょう。デマに惑わされず、テレビやラジオ、自治体の防災無線などから正確な情報を得るように努めてください。避難が必要な場合は、事前に決めておいた避難場所に、非常持ち出し袋を持って速やかに移動します。エレベーターは使用せず、必ず階段を使いましょう。車での避難は、緊急車両の通行を妨げる可能性があるため、原則として徒歩で避難します。
雪害・火山噴火 特有の注意点
雪害と火山噴火、それぞれの災害特性に応じた具体的な注意点と、命を守るための行動指針を示します。
北海道では、地震だけでなく、特有の気象条件や地理的要因から、雪害や火山噴火への備えも欠かせません。これらの災害は、私たちの生活に特有の影響を及ぼすため、それぞれに応じた適切な知識と対策が必要です。
豪雪・吹雪への事前準備と対応
北海道の雪害は、主に豪雪と猛吹雪によって引き起こされます。豪雪時には、屋根からの落雪や雪下ろし中の事故、交通障害による孤立などに注意が必要です。屋根の雪下ろしは必ず2人以上で行い、命綱やヘルメットを着用するなど安全対策を徹底しましょう。また、軒下には近づかないようにします。猛吹雪の際には、視界がほぼゼロになるホワイトアウト状態が発生し、方向感覚を失い非常に危険です。気象情報で猛吹雪が予想される場合は、不要不急の外出は絶対に避けましょう。
事前の準備としては、除雪用具(スコップ、スノーダンプ、小型除雪機など)の確保と点検、食料・水・燃料(灯油など)・医薬品などの数日間分の備蓄、停電に備えた懐中電灯やラジオ、ポータブルストーブの準備が挙げられます。また、車には防寒具、毛布、スコップ、牽引ロープ、非常食、携帯トイレなどを常に搭載しておき、立ち往生に備えましょう。ガソリンは常に余裕を持たせておくことも重要です。水道管の凍結防止対策として、長期間家を空ける場合は水抜きを行うか、ヒーターを設置するなどの対策が必要です。
火山噴火警戒レベルと避難方法
火山噴火への備えは、まず自分の住んでいる地域や周辺にある活火山の情報を正しく理解することから始まります。気象庁は、火山活動の状況に応じて「噴火警戒レベル」を発表しており、レベル1(活火山であることに留意)からレベル5(避難)までの5段階で危険度を示しています。この噴火警戒レベルの意味を正しく理解し、レベルに応じた行動をとることが重要です。
噴火時には、大きな噴石の飛散、火砕流、融雪型火山泥流、火山ガス、そして広範囲に降る火山灰など、様々な現象が発生します。噴火警戒レベルが引き上げられ、自治体から避難指示や勧告が出た場合は、速やかに指示された避難場所に避難してください。避難する際は、ヘルメットや防災頭巾で頭部を保護し、防塵マスクやゴーグル、濡れタオルなどで口や鼻、目を火山灰から守ります。皮膚の露出を避けるため、長袖・長ズボンを着用しましょう。
降灰に備えて、自宅では窓やドアをしっかりと閉め、隙間を目張りすることも有効です。火山灰は少量でも健康に影響を与える可能性があり、特に呼吸器系や循環器系に持病のある方、小さなお子さんや高齢者は注意が必要です。また、火山灰は水を含むと重くなり、建物を倒壊させる危険性もあるため、屋根に積もった灰は早めに除去する必要がありますが、作業は安全に十分配慮して行ってください。
冬季停電・孤立集落への万全対策
冬季の停電や集落孤立という厳しい状況を乗り越えるための暖房、情報収集、食料・水の備蓄といった具体的な対策を詳述します。
北海道の冬は、気温が氷点下になることも珍しくなく、そのような状況下での停電は生命の危機に直結します。また、大雪や吹雪によって道路が寸断され、集落が孤立することも想定されます。これらの事態に備え、万全の対策を講じておくことが極めて重要です。
停電時も安心な暖房・情報手段
冬季の停電で最も重要なのは暖房の確保です。電気に依存しない暖房器具として、カセットガスストーブや石油ストーブ、薪ストーブなどが挙げられます。これらを使用する際は、一酸化炭素中毒を防ぐため、必ず定期的な換気を行ってください。カセットガスボンベや灯油といった燃料も、十分な量を備蓄しておくことが大切です。また、湯たんぽやカイロ、毛布や寝袋、断熱シートなどを活用し、体温を維持する工夫も重要です。窓に断熱シートを貼ったり、厚手のカーテンを使用したりするだけでも、室内の保温効果が高まります。
情報収集手段としては、電池式のラジオが最も確実です。スマートフォンの充電が切れてしまう可能性を考慮し、必ず用意しておきましょう。予備の電池も忘れずに準備してください。スマートフォンは、モバイルバッテリーを複数用意しておくことで、ある程度の期間は使用可能です。使用する際は、バッテリー消費を抑えるために画面の明るさを調整したり、不要なアプリを終了させたりするなどの工夫が必要です。自治体によっては、防災行政無線で情報を発信している場合もあります。
食料・水の備蓄と管理テクニック
停電や孤立に備え、最低でも3日分、できれば1週間分以上の食料と飲料水を備蓄しておきましょう。食料は、レトルト食品、缶詰、アルファ米、カップ麺、乾パン、栄養補助食品など、調理せずに食べられるものや、カセットコンロで簡単に調理できるものが中心となります。ローリングストック法を活用し、普段から少し多めに食料品を購入し、消費した分を買い足していくことで、常に一定量の備蓄を保ち、賞味期限切れも防げます。飲料水は、1人1日3リットルを目安に準備します。ポリタンクなどに水道水を汲み置きしておくことも可能ですが、定期的な入れ替えが必要です。
カセットコンロとガスボンベも必需品です。ガスボンベは1本で約1時間程度使用できるため、家族の人数や備蓄食料の種類を考慮して十分な量を備蓄しましょう。暖房と調理を兼ねることができる薪ストーブなども、設置可能であれば有効な手段です。
交通網寸断!孤立リスクと準備
大雪や吹雪、土砂災害などにより道路が寸断され、集落が孤立する可能性も考慮しておく必要があります。特に山間部や過疎地域では、救援が到着するまでに時間がかかることもあります。このような事態に備えるためには、日頃からの近隣住民とのコミュニケーションが重要です。安否確認の方法や、食料・燃料の共同備蓄、情報共有の体制などを話し合っておきましょう。高齢者や障害のある方など、災害時に支援が必要な方々への配慮も忘れてはいけません。
個人でできる準備としては、やはり十分な量の食料、水、燃料、医薬品、衛生用品などの備蓄です。孤立が長期間に及ぶ可能性も視野に入れ、可能な範囲で多めに備えておくと安心です。また、情報収集手段としてラジオは必須ですが、孤立した場合には外部との連絡手段が限られるため、スマートフォンのバッテリー対策はより重要になります。ポータブル電源などがあれば、さらに安心感が増すでしょう。天候が悪化する前に、早めに避難するという判断も時には必要です。
最低限備えたい防災グッズリスト
災害時に自分と家族の命を守るために、最低限準備しておくべき防災グッズの具体的なリストと、その選び方のポイントを解説します。
災害はいつ、どこで発生するかわかりません。いざという時に慌てないためにも、日頃から防災グッズを準備し、定期的に点検しておくことが大切です。ここでは、非常用持ち出し袋に入れるべきものと、自宅避難用に備蓄しておくべきものを具体的にリストアップします。
非常用持ち出し袋の中身を点検
非常用持ち出し袋は、避難時に最初に持ち出すものです。リュックサックなど両手が空くタイプのものに入れ、すぐに持ち出せる場所に保管しましょう。中身は定期的に点検し、使用期限や消費期限が切れていないか確認することが重要です。最低限備えておきたいものは以下の通りです。
- 飲料水: 500mlペットボトル2~3本程度。
- 非常食: カンパン、アルファ米、栄養補助食品、飴など、調理不要ですぐにエネルギーになるもの。
- 医薬品: 常備薬、絆創膏、消毒液、包帯、痛み止めなど。持病のある方は必ず処方薬の予備を。
- 貴重品: 現金(小銭も)、身分証明書のコピー、預金通帳のコピー、保険証のコピーなど。
- 情報収集・連絡手段: 携帯ラジオ(予備電池も)、スマートフォン、モバイルバッテリー。
- 照明器具: 懐中電灯(予備電池も)、ヘッドライト、小型ランタン。
- 衛生用品: 携帯トイレ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、歯ブラシ、生理用品、マスク、消毒用アルコール。
- 衣類・防寒具: 下着、靴下、動きやすい服、雨具(レインコート)、アルミ製ブランケット、カイロ。
- その他: 軍手、ロープ、ライターまたはマッチ、筆記用具、メモ帳、家族の写真(はぐれた時用)、ホイッスル、布製ガムテープ、ポリ袋(大小数枚)。
乳幼児がいる家庭では、ミルク、哺乳瓶、離乳食、おむつ、おしりふきなども必要です。高齢者がいる場合は、杖や入れ歯、お薬手帳なども忘れずに。ペットを飼っている場合は、ペットフードや水、リード、トイレ用品なども準備しましょう。
自宅避難を支える備蓄品と量
災害発生後、必ずしも避難所で生活するとは限りません。自宅が無事であれば、自宅で避難生活を送る「在宅避難」が基本となります。そのためには、非常用持ち出し袋とは別に、自宅での生活を支えるための備蓄品が必要です。最低3日分、できれば1週間分以上の備蓄を目指しましょう。家族構成や生活スタイルに合わせて必要なものをリストアップし、計画的に備蓄を進めてください。
- 水: 1人1日3リットルを目安に。飲料水だけでなく、調理や手洗いなどに使う生活用水も考慮。
- 食料: 主食(米、パスタ、カップ麺、餅など)、主菜(缶詰、レトルト食品)、副菜(野菜ジュース、乾燥野菜、海苔など)、調味料。ローリングストック法で管理。
- 燃料・調理器具: カセットコンロとガスボンベ(多めに)、鍋、やかん、ラップ、アルミホイル、紙皿、割り箸。
- 暖房器具(冬季): 電源不要のストーブ(石油、ガスなど)と燃料、湯たんぽ、毛布、寝袋。
- 衛生用品: トイレットペーパー、ティッシュペーパー、簡易トイレまたは凝固剤、ゴミ袋、石鹸、シャンプー(ドライタイプも)、歯ブラシ。
- 生活用品: ランタン、懐中電灯、ラジオ、電池(各種サイズを多めに)、工具類(バール、のこぎり、ハンマーなど)、ブルーシート、新聞紙、ポリタンク(給水用)。
- 医薬品: 救急箱の中身を充実させる。解熱剤、胃腸薬、風邪薬なども。
これらの備蓄品は、押し入れや物置など、分散して保管することも検討しましょう。また、定期的に消費期限を確認し、入れ替えることを忘れないでください。
まとめ:北海道の災害に備え、今日から始める防災対策
北海道の多様な災害リスクに備え、本記事で紹介した具体的な対策を今日から実践することの重要性を強調します。
北海道の厳しい自然環境においては、地震、雪害、火山噴火、そしてこれらが引き金となり得る冬季の広域停電といった複合的な災害リスクへの備えが、私たちの安全な暮らしを守る上で不可欠です。本記事では、それぞれの災害の特性と具体的な対策、そして日頃から準備しておくべき防災グッズについて解説してきました。北海道胆振東部地震のブラックアウトの教訓を忘れず、電源に依存しない生活手段の確保や、情報収集能力の維持がいかに重要であるかを再認識する必要があります。また、雪害や火山災害に対しては、地域ごとのハザードマップを確認し、適切な避難計画を立てることが求められます。この記事で紹介した情報を参考に、ぜひご家庭での防災計画を見直し、必要な備蓄品を準備するなど、今日から具体的な行動を起こしてください。日頃からの小さな意識と着実な準備が、いざという時にあなたとあなたの大切な家族の生命と財産を守る力となるでしょう。他人事と捉えず、自分自身の問題として防災に取り組むことが、安全で安心な北海道の未来へと繋がります。
要約ポイント
- 北海道は地震、雪害、火山の複合災害リスクが高い地域です。
- 特に冬季の停電は深刻な影響があり、電源不要の暖房や十分な備蓄が不可欠です。
- 北海道胆振東部地震の教訓から、広域停電への備えの重要性が増しています。
- 各家庭での防災計画、避難経路の確認、防災グッズの準備を日頃から行いましょう。
よくある質問(FAQ)
北海道の冬の停電対策として、具体的にどのような暖房器具を準備すれば良いかを解説します。
Q1: 北海道で冬の停電に備える際、どんな暖房器具が有効ですか?
A1: カセットガスストーブや石油ストーブなど、電源不要の暖房器具が有効です。使用時は換気を徹底し、一酸化炭素中毒に注意してください。燃料も十分に備蓄しておくことが大切です。小型の発電機があれば、電気毛布なども使用できる場合がありますが、燃料の備蓄と騒音、排気ガスに注意が必要です。
災害発生時に正確な情報を得るために、どのような方法があるかを説明します。
Q2: 災害時に信頼できる情報を得るにはどうすれば良いのでしょうか?
A2: スマートフォンの防災アプリ(例:Yahoo!防災速報、NHKニュース・防災アプリなど)、電池式ポータブルラジオ、自治体の防災行政無線や広報車からの情報が信頼できます。SNSの情報はデマや不確実な情報が含まれる可能性もあるため、必ず公的機関(気象庁、自治体、警察、消防など)の発表と照合するようにしましょう。
北海道の雪害に対して、個人でできる具体的な準備について説明します。
Q3: 北海道の雪害に備えて、個人ではどのような準備をすれば良いでしょう?
A3: 除雪用具(スコップ、スノーダンプ、ママさんダンプ等)の用意と点検、数日分の食料・水・燃料(灯油など)の備蓄、停電対策としての照明器具や暖房器具の準備が基本です。不要不急の外出を控える判断も重要です。車で外出する際は、防寒具、非常食、スコップ、毛布、牽引ロープ、ブースターケーブル、携帯トイレなどを必ず携行し、燃料は常に満タン近くを保ちましょう。
火山噴火の予兆があった場合、どのような点に注意して情報を集めるべきかを解説します。
Q4: 火山噴火の兆候がある場合、何に注意して情報を確認すべきですか?
A4: 気象庁が発表する「噴火警報」や「噴火警戒レベル」、そして地元自治体からの避難指示・勧告に最も注意を払いましょう。テレビ、ラジオ、インターネットの信頼できるニュースサイトなどで最新情報を常に確認し、指示に従って冷静に行動することが肝心です。また、事前に居住地域の火山ハザードマップを確認し、避難経路や避難場所を把握しておくことも重要です。
停電時にスマートフォンのバッテリーを長持ちさせるコツはありますか?
Q5: 停電した際、スマートフォンの充電をできるだけ持たせるにはどうしたら良いですか?
A5: まず画面の明るさを最低限にし、Wi-FiやBluetooth、GPSなど不要な通信機能をオフにします。モバイルデータ通信も必要な時だけオンにし、バックグラウンドで動作するアプリを停止させたり、省電力モードに設定したりするのも有効です。そして何よりも、大容量のモバイルバッテリーを複数準備しておくことが最も効果的な対策と言えるでしょう。
参考リンク

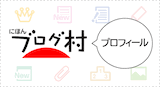
コメント