
※本記事はPRを含みます
改正災害対策基本法・救助法とは?能登の教訓と25年新体制
2025年5月28日、私たちの暮らしと安全に深く関わる「災害対策基本法」および「災害救助法」が改正され、成立しました。この法改正は、2024年1月に発生し、私たちの記憶に新しい令和6年能登半島地震における甚大な被害と、その対応の中で浮き彫りになった多くの教訓を真正面から受け止め、将来起こりうる大規模災害への備えを一層強化することを目的としています。特に、従来の画一的な「場所(避難所)」中心の支援から、被災者一人ひとりの多様な状況やニーズに寄り添う「人への支援」へと、国の防災・減災に関する基本思想の大きな転換点が示されたことは特筆すべき点です。この重要な法改正によって、国の防災体制はどのように変わり、私たちの生活にはどのような影響がもたらされるのでしょうか。また、私たちは今後、どのように備えていくべきなのでしょうか。本記事では、これらの疑問に答えるため、最新の法改正の主要なポイントを、背景とともに分かりやすく解説していきます。具体的には、防災の司令塔となる「防災監」の新設、災害の定義への「地盤の液状化」の追加、そして被災者支援を格段に進める「福祉サービスの提供」の明記など、多岐にわたる改正内容を掘り下げていきます。
この記事では、2025年に改正された災害対策基本法と災害救助法について、その背景となった令和6年能登半島地震の教訓から、具体的な法律の変更点、そして私たちの生活や防災への取り組みにどのような変化が求められるのかまで、幅広く掘り下げて解説します。以下の目次から、特に関心のある項目を選んでお読みいただくことも可能です。ぜひ、最新の防災知識をアップデートし、万が一の事態に備えるための一助としてください。各章では、法改正のポイントだけでなく、それが私たちの実生活にどう関わってくるのか、そして私たち自身が何をすべきかについても触れていきます。
目次
2025年災害法改正の背景:令和6年能登半島地震の重い教訓
今回の災害対策基本法および災害救助法の改正は、私たちの記憶にも新しい令和6年能登半島地震における甚大な被害と、その対応の中で浮き彫りになった数々の課題が直接的な契機となっています。未来の災害で同様の悲劇を繰り返さないため、そしてより迅速かつ的確な被災者支援を実現するために、国を挙げて防災体制を見直す必要に迫られました。この地震では、建物の倒壊や津波、土砂災害、火災といった直接的な被害に加え、インフラの寸断による孤立集落の発生や、避難生活の長期化に伴う健康問題、いわゆる「災害関連死」も深刻な問題となりました。
未曾有の被害と浮き彫りになった課題
令和6年能登半島地震では、200名を超える方が犠牲となり(関連死を含む、2025年5月時点)、多くの家屋が全半壊しました。特に奥能登地域では、道路網が寸断され多数の集落が孤立状態に陥り、支援物資の輸送や救助活動が著しく困難となりました。エネルギー供給(電気・ガス・水道)や通信インフラも広範囲で長期間にわたり途絶し、被災者の生活に深刻な影響を与えました。避難所の運営においても、食料や水、医薬品の不足、プライバシーの確保の難しさ、衛生環境の悪化、寒さ対策の不備などが指摘され、高齢者や持病を持つ方、障害のある方、妊産婦や乳幼児を抱える家庭など、特に配慮が必要な人々への支援が行き届きにくい状況も散見されました。情報伝達の混乱やデマの拡散も、被災者の不安を増大させる一因となりました。これらの経験は、既存の防災体制や法制度の限界を露呈させ、抜本的な見直しの必要性を示唆したのです。また、復旧が進む中で発生した奥能登豪雨は、複合災害の恐ろしさと、復興過程における継続的な自然災害リスクへの備えの重要性を改めて突きつけました。
「場所の支援」から「人への支援」への理念転換とは
従来の災害支援は、指定された避難所の開設や、そこでの食料・毛布といった物資の配布など、「場所」を基点とした画一的な対応が中心でした。しかし、能登半島地震では、自宅が無事でもライフラインの途絶により避難所生活を選択せざるを得ない方、逆に自宅に留まりたいと考える在宅避難者、やむを得ず車中泊を選択する方、さらには福祉施設や医療機関に入所・入院中の被災者など、極めて多様な状況下にある人々への支援が必要となりました。こうした状況を踏まえ、中央防災会議が2024年11月に取りまとめた「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について」では、従来の画一的な「場所(避難所)の支援」から、個々の被災者の具体的なニーズや生活状況、健康状態、家族構成などをきめ細かく把握し、それぞれに最適化された支援を届ける「人(避難者等)の支援」へと、国の災害対応の基本理念を大きく転換すべきであるとの提言がなされました。今回の法改正は、この理念転換を具現化するための重要なステップと言えます。被災者一人ひとりの尊厳を守り、きめ細やかなサポートを提供することで、誰一人取り残さない支援を目指す姿勢が鮮明になっています。
「場所の支援」と「人の支援」の比較
| 項目 | 従来の「場所の支援」 | 新たな「人の支援」 |
|---|---|---|
| 支援の中心 | 避難所、物資配布 | 個々の被災者のニーズ、生活状況 |
| 主な対象者 | 主に避難所にいる人々 | 在宅避難者、車中泊者、施設入所者など多様な被災者 |
| 主な支援内容 | 画一的な物資提供、避難場所の提供 | 個別化されたサポート(健康、福祉、生活再建など) |
| 情報把握 | 避難者名簿(避難所ごと)が中心 | 多様な状況下の被災者情報を網羅的に把握(防災DX活用) |
| 目指す姿 | 生命の安全確保、応急的な生活維持 | 尊厳の維持、きめ細やかなケア、誰一人取り残さない生活再建支援 |
【改正災害対策基本法】5つの主要変更点と私たちの備え
今回の災害対策基本法の改正は、国の防災体制の根幹を強化し、より実効性の高い被災者保護を目指すものです。特に、司令塔機能の明確化、災害の定義拡大、行政の責務追加、防災DXの推進、そして情報共有と民間連携の強化が大きな柱となっています。これらの変更点を理解することは、私たち自身の防災意識を高め、適切な備えに繋がります。以下に主な変更点をまとめました。
改正災害対策基本法の主要変更点サマリー
| 変更ポイント | 主な内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 1. 「防災監」の新設 | 内閣府に次官級ポスト「防災監」を設置 | 政府の司令塔機能強化、迅速な初動対応、省庁横断連携 |
| 2. 災害定義に「地盤の液状化」追加、宅地耐震化推進 | 液状化被害を「災害」と明記、宅地耐震化を努力目標に | 液状化対策・支援強化、宅地の安全性向上促進 |
| 3. 行政努力目標の拡充 | 「被災者の生活再建」「先端技術活用」等を明記 | 中長期的な被災者支援充実、防災分野での技術革新促進 |
| 4. 「防災DX」推進、自治体備蓄公表義務化 | マイナンバーカード活用、オンライン手続き推進、備蓄情報公開 | 情報共有効率化、支援の迅速化・透明化、住民の防災意識向上 |
| 5. 被災者情報共有強化、援護協力団体登録制度 | 自治体間の情報提供義務化、NPO等民間団体登録制度創設 | 広域避難時の支援継続、多様な民間の力の活用、専門的支援の提供 |
ここでは、これらの5つの主要な変更点について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1) 内閣府に「防災監」新設:司令塔機能の強化
大規模災害発生時における政府の対応力を抜本的に強化するため、内閣府に総理大臣直属の次官級ポストとして「防災監」が新設されました。防災監は、災害発生初期から復旧・復興に至るまで、各省庁の縦割りを排し、政府一体となった迅速かつ強力な指揮命令系統を確立する役割を担います。具体的には、総理大臣の指示に基づき、関係省庁の長に対して必要な指示を行い、情報の集約と的確な判断、そして省庁横断的な資源(人員、物資、予算等)の配分をスムーズに行うことで、より効果的かつ効率的な災害対応を実現することが期待されています。これにより、例えば被災地への緊急物資輸送や専門家チームの派遣などが、これまで以上に迅速に行われる体制が整います。従来の防災担当大臣に加え、実務レベルでの強力な調整権限を持つポストを設けることで、危機管理体制の実効性を高める狙いがあります。
(2) 災害定義に「地盤の液状化」追加と宅地耐震化
これまで必ずしも法律上の「災害」として明確に位置づけられていなかった「地盤の液状化」による被害が、今回の改正で正式に災害対策基本法上の「災害」として定義されました。令和6年能登半島地震でも広範囲で液状化現象が発生し、家屋の傾斜や沈下、ライフラインの寸断など深刻な被害をもたらしたことを受けた措置です。これにより、液状化被害を受けた地域への国の財政支援や復旧事業が講じやすくなり、被害調査や対策技術の開発も促進されることが期待されます。あわせて、国や地方公共団体の責務として「宅地の耐震化」が行政の努力目標として明記されました。これは、個々の建物の耐震性だけでなく、その建物が立つ地盤を含めた宅地全体の安全性を向上させるための取り組みを国や自治体が支援し、推進していくことを意味します。液状化対策としての地盤改良工事や、擁壁の強化、造成地の安全対策などがこれに該当し、住民への啓発や技術的支援、費用助成なども検討される可能性があります。
(3) 行政の努力目標を拡充:生活再建と先端技術活用を明記
被災された方々が一日も早く元の生活を取り戻し、安心して暮らせるよう、国の責務として「被災者の生活の再建に関する事項」が行政の努力目標に明確に位置づけられました。これは、単に避難所の提供や応急的な住まいの確保といった短期的な支援にとどまらず、生活資金の支援制度の充実、住宅再建への助成、就労支援、心のケア、被災した子どもたちへの学習支援、地域コミュニティの再構築など、中長期的な視点に立った多岐にわたる支援の充実を目指すものです。被災者一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援計画の策定や、相談体制の強化などが求められます。また、「防災上必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項」も努力目標として追加されました。これにより、AI(人工知能)を活用した被害予測や避難誘導の最適化、ドローンを用いた被災状況の迅速な把握や物資輸送、ビッグデータを活用した避難行動分析、オンラインでの各種申請手続きの円滑化など、最新技術を防災・減災対策や被災者支援に積極的に取り入れていく方針が示されました。これらの技術活用により、より科学的根拠に基づいた効率的な防災活動と、被災者への迅速かつ的確な情報提供が可能となることが期待されます。
(4) 「防災DX」推進と自治体備蓄の公表義務化
デジタル技術を駆使して防災力を強化する「防災DX(デジタル・トランスフォーメーション)」の推進が、法改正により一層加速します。具体的には、マイナンバーカードを活用した被災者名簿の迅速な作成・共有や、個々の被災状況に応じたプッシュ型の支援情報提供(例えば、避難勧告、給付金申請、医療相談窓口の情報などを個別に通知)、オンラインでの罹災証明書発行手続きの簡素化などが想定されています。これにより、行政手続きの効率化はもちろん、支援が必要な人に適切なサポートがより早く、より確実に届く体制を目指します。情報伝達手段の多重化・強靭化も図られ、災害時でも途絶しにくい情報ネットワークの構築が進められます。さらに、地方公共団体に対しては、保有する備蓄物資(食料、水、毛布、医薬品、簡易トイレなど)の種類や数量、保管場所などを住民に分かりやすい形で公表することが義務付けられました。これは、地域の防災力を住民自身が正確に把握し、家庭での備蓄(自助)や近隣住民との協力(共助)の意識を高めること、そして災害時には自治体間で不足する物資を迅速に融通し合う広域的な連携を円滑化する狙いがあります。住民は公表情報を基に、自宅での備蓄とのバランスを考えたり、最寄りの避難所の備蓄状況を事前に確認したりすることが可能になります。
(5) 被災者情報共有の強化と援護協力団体の登録制度
大規模災害時には、被災者が住み慣れた地域を離れて遠隔地の親族宅や自治体が用意した避難施設へ広域に避難することも少なくありません。このような場合に、避難先の自治体が避難者の情報を正確に把握し、必要な支援(健康管理、就学支援、公営住宅の斡旋など)を継続的に提供できるよう、関係する地方公共団体間での被災者情報の提供が新たに義務化されました。個人情報保護に配慮しつつ、必要な情報を迅速かつ安全に共有するための仕組みづくりが求められます。これにより、安否確認の迅速化や、途切れることのない医療・福祉サービスの提供に繋がることが期待されます。また、専門的なスキルや機動力、そして豊富な経験を持つNPOやボランティア団体など、民間組織の力を災害対応により効果的に活かすため、「被災者援護協力団体」の登録制度が創設されました。事前に活動内容や対応可能な地域などを国や都道府県に登録した団体は、災害発生時に行政と円滑に連携し、それぞれの専門性を活かした被災者支援活動(炊き出し、物資輸送、医療・看護、心のケア、外国語通訳、障害者支援、ペット支援など)を組織的かつ効果的に展開できるようになります。この制度により、多様化・複雑化する被災者ニーズに対して、より専門的できめ細やかな支援が提供される体制が強化されることになります。
(?s)\s* \s*` (?s)\s* \s*` (?s)\s* \s*`
【改正災害救助法】72年ぶり大改正:「福祉サービスの提供」新設
災害救助法は、被災者の応急的な救助を目的とする法律ですが、今回の改正では、実に72年ぶりとなる大幅な見直しが行われました。その最大のポイントは、救助の種類に「福祉サービスの提供」が新たに明記されたことです。これにより、被災された方々、特に高齢者や障害のある方、乳幼児を抱える家庭など、特別な配慮が必要な方々への支援が、法律に基づいてより確実に提供される道が開かれました。これまでの救助は、避難所の設置や食料・水の供給、医療・助産、住宅の応急修理などが中心でしたが、これらに加えて、被災者の心身の状態に応じた専門的な福祉サポートが明確に位置づけられた意義は非常に大きいと言えます。
「福祉サービスの提供」とは具体的に何か?
新たに追加された「福祉サービスの提供」には、避難所等における介護職員や相談支援専門員によるケア、仮設住宅等での見守り活動、被災による精神的な負担を軽減するためのカウンセリング、障害のある方へのコミュニケーション支援(手話通訳者の派遣など)、発達障害のある子どもたちへの専門的なサポートなどが含まれると考えられます。これまでも現場の判断や個別の取り組みとして可能な範囲で対応がなされてきましたが、法律に明記されることで、これらの支援が「応急救助」の一環として正式に位置づけられ、必要な人員(福祉専門職、介護士、精神保健福祉士など)の確保や物資の調達、そしてそれらにかかる費用に対する国の財政的な裏付けがより確実になることが期待されます。例えば、避難所に福祉専門職が巡回し、要配慮者の健康状態や生活上の困りごとを早期に把握し、適切なサービスに繋げたり、仮設住宅で孤立しがちな高齢者への定期的な訪問や声かけ、生活相談を行ったりすることが、より組織的かつ継続的に実施できるようになります。また、被災した障害者施設や高齢者施設の機能回復支援なども視野に入ってくる可能性があります。
「福祉サービスの提供」における具体的な活動例
| 対象となる主な福祉サービス例 | 具体的な内容・活動 |
|---|---|
| 避難所・仮設住宅等でのケア・相談 | 介護職員・相談支援専門員によるケア、個別相談、見守り活動、安否確認 |
| 精神的・心理的ケア | 臨床心理士・精神保健福祉士等によるカウンセリング、心のケア |
| コミュニケーション支援 | 手話通訳者の派遣、多言語対応、情報伝達の補助 |
| 特定のニーズへの対応 | 発達障害のある子どもやその家族への専門的サポート、医療的ケアが必要な人への連携 |
| 健康・医療との連携 | 保健師等と連携した健康相談、服薬支援、医療機関へのつなぎ支援 |
| 生活再建に向けた相談支援 | 生活相談全般、関連制度の案内、専門家(弁護士、社会福祉士等)への橋渡し |
期待される災害ケースマネジメントとの連携
この「福祉サービスの提供」は、近年その重要性が強く指摘されている「災害ケースマネジメント」と連携することで、その効果を最大限に発揮すると考えられます。災害ケースマネジメントとは、被災者一人ひとりが抱える複雑な課題(住まい、仕事、健康、心の問題、家族関係、地域からの孤立など)に対し、行政の担当者や社会福祉協議会の職員、民生委員、専門職などがチームを組んで寄り添い、個別の状況に応じたきめ細やかな支援計画(ケアプラン)を作成し、生活再建に至るまでをトータルでサポートする包括的な取り組みです。今回の法改正により、災害救助の初期段階から福祉的な視点でのアセスメントや必要な支援が組み込まれることで、その後の生活再建フェーズにおける災害ケースマネジメントへのスムーズな移行と、切れ目のない包括的な支援体制の構築が進むことが大いに期待されます。これにより、被災者が「どこに相談すればよいかわからない」「必要な支援がなかなか届かない」といった事態を防ぎ、安心して生活再建に取り組み、再び自立した生活を送れるようになるための環境づくりに大きく貢献するでしょう。
法改正で私たちの生活・地域防災はどう変わる?
今回の災害対策基本法および災害救助法の改正は、国や自治体の防災体制を強化するだけでなく、私たち住民一人ひとりの防災意識や行動、そして地域コミュニティのあり方にも影響を与えるものです。法改正の趣旨を理解し、それを日々の備えや地域の活動に活かしていくことが、より安全・安心な社会の実現に繋がります。具体的にどのような変化があり、私たちはどう対応すべきかを見ていきましょう。
自助・共助・公助における主な行動変化とポイント
| 取り組み | 主な行動例・ポイント | 関連する法改正の側面 |
|---|---|---|
| 自助 (自分で自分を守る) |
家庭での備蓄(食料・水・医薬品等最低3日~1週間分)、避難場所・経路確認、ハザードマップ確認、家族との安否確認方法の取り決め、防災アプリ等の活用・習熟 | 自治体の備蓄状況公表、防災DX推進 |
| 共助 (地域で助け合う) |
自治会・自主防災組織への参加、防災訓練・ワークショップ参加、近隣住民との連携(声かけ、要配慮者支援体制づくり)、地域ハザードマップ共有 | 被災者援護協力団体登録制度 |
| 公助 (行政等による支援) |
行政の防災情報(備蓄状況、避難情報等)の確認・活用、防災訓練・セミナー参加、行政・支援団体との連携、法改正内容の理解と適切な制度利用 | 防災監設置、福祉サービス提供、被災者情報共有強化 |
自助・共助:住民一人ひとりに求められる意識と行動
まず「自助」、つまり自分自身の命や財産を自分で守るための取り組みが一層重要になります。今回の法改正で自治体による備蓄物資の状況公表が義務化されたことを受け、お住まいの地域の公表情報を確認し、それを踏まえて家庭での食料、水、医薬品、簡易トイレ、モバイルバッテリーなどの備蓄内容を改めて点検・拡充することが推奨されます。最低でも3日分、可能であれば1週間分以上の備蓄が望ましいとされています。また、避難場所や複数の避難経路の再確認、ハザードマップによる自宅周辺のリスク把握、家族との安否確認方法(災害用伝言ダイヤル171やSNSの活用など)の具体的な取り決めなど、基本的な備えを徹底することが、いざという時の行動に繋がります。「防災DX」の推進により、今後はスマートフォンなどを活用した災害情報の入手(自治体の防災アプリ、気象庁の情報、信頼できるニュースサイトなど)や安否確認サービスが一層重要になるため、平時から操作に慣れ親しんでおくことも大切です。
次に「共助」、つまり地域やコミュニティで互いに助け合う取り組みも、法改正の趣旨を踏まえて強化していく必要があります。「被災者援護協力団体」の登録制度が創設されたように、地域における多様な主体(自治会、自主防災組織、NPO、企業など)との連携が一層重視されます。自治会や自主防災組織が実施する防災訓練やワークショップに積極的に参加し、防災知識や応急手当のスキルを身につけること、近隣住民との日常的な声かけや挨拶を通じて良好な関係を築き、災害時要援護者(高齢者、障害のある方、乳幼児のいる家庭など)を把握し助け合える体制を作っておくこと、地域のハザードマップを共有し危険箇所や安全な避難ルートを共に認識するなど、日頃からのコミュニティづくりが、大規模災害発生時の大きな力となります。特にマンションなど集合住宅では、管理組合を中心とした防災マニュアルの整備や安否確認訓練などが有効です。
公助:行政・支援団体によるサポート体制の進化
「公助」、つまり行政や専門機関による支援も、今回の法改正によってさらなる進化が期待されます。「防災監」の設置による迅速かつ的確な初動対応体制の確立、液状化対策を含む宅地の安全性向上への取り組みの推進、「福祉サービスの提供」の明記による高齢者や障害者など要配慮者への専門的支援の強化などはその代表例です。また、被災者情報の自治体間での共有化が進むことで、広域避難した場合でも避難先で必要な情報提供や行政サービス(例えば、公営住宅への一時入居、子どもの就学支援など)をスムーズに受けやすくなるでしょう。自治体の備蓄状況が公表されることは、行政サービスの透明性が高まるとともに、住民からの具体的な意見や要望を今後の防災計画に反映させやすくなるという側面もあります。
私たち住民は、これらの行政サービスの変化を正しく理解し、パンフレットやウェブサイト、説明会などを通じて情報を収集し、必要に応じて適切に活用していくことが求められます。また、行政や消防、警察、社会福祉協議会、日本赤十字社といった支援団体が提供する防災訓練やセミナー、講習会に積極的に参加し、最新の防災知識や救助技術、応急手当の方法などを習得することも、自分自身や家族、そして地域全体の防災力向上に不可欠です。これらの機会を通じて、行政や支援団体と顔の見える関係を築いておくことも、いざという時の連携を円滑にするでしょう。
まとめ:2025年新災害法制を理解し、未来の災害に備えよう
2025年5月に成立した改正災害対策基本法および改正災害救助法は、令和6年能登半島地震という未曾有の災害から得られた多くの貴重な教訓を未来へ繋ぐための、国の防災・減災戦略における大きな一歩と言えます。「場所の支援」から「人への支援」へという理念の転換を核に、国の司令塔機能の強化としての「防災監」の新設、災害の実態に合わせた定義の見直し(「地盤の液状化」追加)、行政の努力目標としての「被災者の生活再建」や「防災DX」の明記、そして災害救助法における72年ぶりの「福祉サービスの提供」の追加など、その内容は多岐にわたります。これらの改正は、国や自治体の責務を強化するだけでなく、私たち国民一人ひとりに対しても、自助・共助の取り組みを一層深化させることを求めています。
本記事で解説した改正のポイントを正しく理解し、日頃の備えを見直し、地域社会との連携を深めることが、将来起こりうる大規模災害から自分自身と大切な人の命、そして私たちの暮らしを守るために不可欠です。災害はいつ、どこで発生するかわかりません。しかし、最新の情報を基にした正しい知識と具体的な備えがあれば、被害を最小限に抑え、困難を乗り越える力となります。この法改正を他人事と捉えず、自分たちの問題として考え、常に最新の情報に関心を持ち、家庭で、地域で、職場で、できることから防災・減災への取り組みを始めていきましょう。この記事が、その一助となれば幸いです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2025年の災害関連法改正で、最も重要なポイントは何ですか?
A1. 令和6年能登半島地震の教訓を深く反映し、国の防災体制の司令塔「防災監」の新設、災害対策基本法における「被災者の生活再建」の明記、そして災害救助法に72年ぶりに「福祉サービスの提供」が追加され、「人」を重視したきめ細やかな支援への転換が図られた点が最も重要です。これにより、より迅速で実効性の高い災害対応と、多様な被災者ニーズに応じた支援の充実が目指されています。
Q2. 新設される「防災監」とは、具体的にどのような役割を担うのですか?
A2. 内閣府に置かれる次官級のポストで、大規模災害発生時に内閣総理大臣の指示を直接受け、関係省庁に対する指示や調整を行い、政府一体となった災害対応の強力な司令塔機能を担います。これにより、情報集約の迅速化、的確な状況判断に基づく省庁横断的な資源配分、そして被災地への迅速な支援提供など、より効果的かつ効率的な初動対応や復旧支援が期待されます。
Q3. 改正災害救助法に追加された「福祉サービスの提供」によって、被災者支援はどう変わりますか?
A3. これまでの物資提供や避難所設営といった応急救助に加え、被災者の心身のケア、介護、相談支援といった専門的な福祉的サポートが災害救助の対象として明確化されました。これにより、避難所だけでなく在宅被災者や仮設住宅居住者など、多様な状況にある被災者一人ひとり(特に高齢者、障害者、乳幼児等)に対し、専門職による個別的かつ継続的な福祉支援が行き届きやすくなることが期待されます。災害ケースマネジメントとの連携も重要になります。
Q4. 「防災DX」の推進とは、具体的にどのような取り組みが進められるのですか?
A4. デジタル技術を活用して、被災者情報の収集・共有の迅速化(例:マイナンバーカード利用)、必要な物資の効率的な供給管理、オンラインでの罹災証明申請手続きの簡素化・迅速化など、災害対応のあらゆる場面での効率化・高度化を図る取り組みです。これにより、よりスムーズで的確な被災者支援、プッシュ型での情報提供、そして行政手続きの負担軽減を目指します。自治体の備蓄状況公表もその一環です。

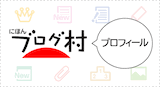
コメント