
「地震が起きてからホームセンターに走っても、棚は空っぽだった…」
2025年12月8日午後11時15分頃、青森県東方沖でマグニチュード(Mw)7.5の地震が発生しました。岩手県や青森県のホームセンターでは翌日、即席スープや防寒グッズ、家具転倒防止用品が瞬く間に売り切れとなりました。
気象庁は今回、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。これは単なる余震への注意ではありません。世界の事例では、Mw7.0以上の地震が起きた後、7日以内に Mw8クラス(Mw7.8以上)の巨大地震が起きたケースが「おおむね100回に1回程度」あるとされています。
平常時よりも巨大地震の可能性が相対的に高まっているため、「今だけは普段以上の備えが必要」という警告です。
※この情報は「予測」ではなく、過去事例に基づく確率評価であり、発生を断定するものではありません。
「災害は、忘れた頃にやってくる」
喉元過ぎれば熱さを忘れる、で終わらせてはいけません。この記事では、一過性のパニック買いではなく、「日常の中で無理なく続けられる、家族を守るための最強の備え」をリスト化しました。

この記事のナビゲーター「クロマル」だにゃ!
みんな怖くて買いに走ったけど、大事なのは「その後」だにゃ。今日からできる「命の守り方」を一緒にチェックするにゃ!
【新常識】2026年の防災は「フェーズフリー」が基本
「後発地震注意情報」の対象地域(北海道から千葉県の182市町村)にお住まいの方はもちろん、全国どこでも「もしも」は突然訪れます。
今、主流となっているのが「フェーズフリー」という考え方です。キャンプ用品を日常的に使ったり、保存のきく美味しいスープを普段の食事に取り入れたりする。「日常(いつも)」と「非常時(もしも)」の垣根をなくすことで、災害時にも普段通りの生活レベルを維持しやすくなります。
例として、普段からアウトドアチェアや折りたたみテーブルを使っておけば、停電時の在宅避難や避難所でもそのまま“マイ椅子・マイテーブル”として使えます。

クロマル:「防災用」って書いてなくても、キャンプ道具や美味しいレトルト食品は立派な防災グッズだにゃ。
【命を守る】家の中の安全対策チェックリスト
※今すぐやるべき優先順位:①寝室固定 → ②ガラス対策 → ③テレビ
地震発生の瞬間、あなたの命を守るのは「防災リュック」ではなく「家具の固定」です。特に津波の心配がない内陸地域でも、建物の倒壊や家具の転倒が命取りになります。
家具転倒防止:L字金具と突っ張り棒
寝ている場所にタンスや本棚が倒れてきたら、逃げることさえできません。就寝中の無防備な状態を守るため、寝室の対策は最優先です。
優先対策リスト
- 背の高い家具:L字金具(壁にネジ止め)が最強ですが、賃貸なら「強力突っ張り棒」と「粘着マット」の併用が必須です。
- テレビ・冷蔵庫:耐震ジェルマットで足元を固定します。
- ガラス窓:飛散防止フィルムを貼り、避難経路がガラスの破片で塞がれるのを防ぎます。
枕元には、ガラス片対策として折りたたみスリッパと軍手を置いておきましょう。
家の修理やリフォームが必要な場合は、事前に点検しておくことも重要です。

クロマル:地震の揺れで怪我をしないことが、避難の第一歩だにゃ。まずは寝室だけでも固定するにゃ!
【逃げる備え】非常用持ち出し袋(1次避難)の厳選リスト
※津波・火災想定地域の人はここが最優先
「津波警報・注意報が出たら、すぐ逃げる」。これは鉄則です。
久慈港では、第1波到達から約1時間半後の第5波が最大となり、70cm程度の津波が観測されたと東北大学の解析で示されています。**津波は第1波が最大とは限らず、複数の波が襲来する**という原則を忘れないでください。一度背負ったら戻らない覚悟で、必要最小限の荷物をまとめましょう。
「重すぎて走れない」を防ぐ!厳選チェックリスト
欲張りすぎると動けなくなります。男性15kg、女性10kgを目安に、「命をつなぐもの」に絞ります。
| カテゴリ | 必須アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| 安全確保 | ヘルメット、運動靴、保護ゴーグル、レインコート | 落下物・粉じん対策。ホイッスルも。 |
| 貴重品 | 現金(小銭)、身分証コピー | 公衆電話用に10円玉・100円玉を多めに。筆記用具(油性マジック)。 |
| 救急・衛生 | 救急セット、携帯トイレ、マスク | 三角巾、包帯、消毒液も必須。 |
| 情報・光 | スマホ、充電器、ヘッドライト | 両手が空くヘッドライトを推奨。耳栓・アイマスクで安眠確保。 |
| 防寒(冬) | アルミシート、カイロ、簡易マット | 12月の被災では低体温症が命に関わります。床からの冷え対策。 |
| 水・食料 | 浄水器、水500ml×2、高カロリー菓子 | 水は重いので浄水器があると安心。 |
▼救急セット(止血・固定用)と三角巾
初期の怪我への応急手当ができるセットも忘れずに。
 |
救急セット 20点 救急基本セット 事業所 労働安全衛生規則 日本製 ケース 持運び 楽な 軽い 医薬部外品 家庭 ファミリー 防災 S ホワイト F-2485 |
![]()
 |
![]()
▼粉じん・飛散物対策の保護ゴーグル
 |
[山本光学] 保護ゴーグル YG-1100 メガネの上からかけられる 耐久性20倍でくもらない【PAF(パフ)】 日本製 JIS 紫外線カット |
![]()
冬の被災に特化した「プラスワン」
岩手・青森での教訓の通り、冬の停電時は「寒さ」が最大の敵です。以下のアイテムは必ず追加してください。
▼落下物から頭を守る!折りたたみヘルメット
場所を取らずに収納でき、いざという時にサッと組み立てられます。
 |
![]()
▼かさばらずに体温を守る!静音アルミシート
ガサガサ音がしないタイプなら、避難所でも周囲に気兼ねなく使えます。
 |
Eco Ride World アルミシート エマージェンシーシート カサカサ音が少ない 静音 ブランケット アルミブランケット サバイバルシート 備蓄 防災 保温 (3) sb_126-02 |
![]()
▼両手が自由に!避難時の必須ライト&閉じ込め対策ホイッスル
 |
GENTOS(ジェントス) LED ヘッドライト USB充電式(専用充電池/単4電池) 320ルーメン 釣り ダブルスター WS-343HD 赤色サブLED |
![]()
 |
![]()
▼両手が空くポンチョ型が便利!レインコート
防寒・防風にも役立つ撥水性の高いポンチョがおすすめです。
 |
![]()

クロマル:冬の夜に逃げるのは本当に寒いんだにゃ。アルミシート一枚あるだけで、生存率が全然違うにゃ!
【留まる備え】在宅避難(2次避難)のための備蓄術
※優先順位:①トイレ・水 → ②熱源・食料 → ③電源確保
家が無事なら、避難所へ行かずに自宅で過ごす「在宅避難」が基本です。しかし、電気・ガス・水道が止まった家は、ただの「箱」です。そこで生き抜くための装備を整えましょう。
家族4人の備蓄目安(1週間分)
※農林水産省「災害時に備えた食品ストックガイド」等を参考に算出
1. 【最重要】トイレ対策:水は流せません!
断水時、トイレの水は絶対に流してはいけません。2024年能登半島地震では、断水でトイレが使えない状態が長期化し、不衛生な環境からノロウイルスなどの感染症リスクが問題になりました。
実際に災害関連死も多数報告されており、トイレ環境の確保が健康被害を防ぐうえで極めて重要だと指摘されています。100均の小分けパック(10回分程度)では、家族4人の場合たった半日で尽きます。大容量の凝固剤と、臭わない袋が必須です。
▼臭い対策ならこれ一択!医療向け開発の防臭袋BOS
 |
【うんちが臭わないトイレ】 BOS非常用トイレ (Bセット) 30回分 災害/携帯/簡易トイレ/15年保存 ◆防臭 防菌◆ 臭わない袋BOS付き 防災グッズ |
![]()
水と運搬:ポリタンク・給水タンクの備え
飲料水はペットボトルでの備蓄が基本ですが、断水時に給水所から自宅へ生活用水を運ぶためのポリタンク(給水タンク)も必須です。自治体の給水活動でもポリタンクがないと水を受け取れません。折りたたみ式のウォータータンクなら、普段の収納に困りません。
▼給水所からの運搬に必須!20L ポリタンク(コック付き)
 |
![]()
▼折りたためて省スペース!抗菌ウォータータンク(5L)
 |
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) ポリタンク ウォータータンク ウォータージャグ 抗菌タイプ 5L オリーブ ボルディー UE-2031 |
![]()
2. 食料・熱源:温かい食事で心を保つ
冬の災害で冷たいご飯だけでは、体も心も冷え切ってしまいます。カセットコンロとガスボンベは、ライフライン停止時の最強の命綱です。
▼アウトドア兼用の最強コンロ!風に強い「タフまる」
 |
Iwatani イワタニ 岩谷 カセットコンロ カセットフー タフまる ケース付き キャンプ アウトドア BBQコンロ 停電対策 ブラック 日本製 CB-ODX-1-BK |
![]()
3. 寒さ・電源対策:停電時の「光と暖」
停電すると、エアコンもファンヒーターも止まります。今回の地震でも、電池だけで動く石油ストーブが飛ぶように売れました。
⚠️【重要警告】石油ストーブ使用時の注意
停電時に石油ストーブを屋内で使用する場合、不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒のリスクが非常に高くなります。取扱説明書に記載された換気・使用方法を守ることが大前提です。
- 換気が絶対条件:1時間に1~2回、必ず窓を開けて換気してください。
- 就寝中・外出中は消火:寝ている間に不完全燃焼が起きると、気づかずに命を落とします。
- 高気密住宅:換気扇が回らない停電時は特に空気がこもります。少し窓を開けて使用するなどの対策が必要です。
▼スマホ充電も寒さ対策も!ポータブル電源
電気毛布を使えば、火を使わずに安全に暖を取ることができます。
 |
![]()
自家発電・蓄電で停電を乗り切る
ポータブル電源に加え、太陽光発電や家庭用燃料電池(エネファーム)は、停電時も家庭で電力を賄う「究極の在宅避難」を可能にします。特にオール電化住宅では、これらの設備があることで災害時のリスクを大幅に下げることができます。
4. 衛生・清潔ケア:お風呂に入れないストレス対策
水が出ない日が続くと、身体の不快感は精神的ストレスになります。
▼水なしで頭皮スッキリ!ドライシャンプー
 |
【Amazon.co.jp限定】FRESSY 【まとめ買い】フレッシィ ドライシャンプー スプレータイプ 150mL×3個 おまけ セット |
![]()
その他便利アイテム(水・衛生・調理の節約)
在宅避難が長期化する場合、水を節約し、衛生を保つための日用品は必須です。
- ラップ・アルミホイル・紙皿:食器洗いに使う水の節約になります。ラップで包めば、紙皿の使い回しも可能です。
- ゴミ袋・ポリ袋(多め):多用途で大活躍。簡易バケツ、防水、簡易カッパ、トイレ補助、怪我の応急処置など、いくらあっても困りません。
- ガムテープ(布テープ):破損した箇所の応急処置、避難所での荷物への名前書きや目印付けにも使えます。
【家族構成別】要配慮者・ペットの備えチェック
一般的なリストに加え、家族の中に支援が必要な人や動物がいる場合、専用の備えが命運を分けます。特に**常備薬やアレルギー対応品**は公的な支援が遅れる可能性があるため、自宅での備蓄が必須です。
追加検討が必要なアイテム
- 乳幼児がいる場合:紙おむつ、おしりふき、粉ミルク/液体ミルク、ベビーフード(アレルギー配慮含む)、母子手帳のコピー。
- 高齢者・持病のある方:1週間分以上の常用薬、お薬手帳のコピー、予備のメガネ、介護用おむつ、とろみ剤、入れ歯洗浄剤。
- 女性の方:生理用品(多め)、下着の替え、ウェットティッシュ。
- ペットがいる場合:フード、水(5日分以上)、リード、キャリーケース、トイレ用品。**環境省ガイドライン**に従い、普段から「同行避難」の訓練をしましょう。
あわせて、お住まいの自治体がペット同行避難をどこまで受け入れているか、事前に公式サイトで確認しておくと安心です。 - ひとり暮らしの場合:緊急連絡先や持病・服用薬を記載したカードを財布やスマホケースに入れておくと、万一のときに支援を受けやすくなります。
【つながる備え】家族の連絡ルールと情報収集
災害時は回線が混雑し、電話は繋がらなくなります。SNSや災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を、平時に練習しておきましょう。
### 情報収集:デマに惑わされない
災害時は不安からデマ拡散しやすくなります。信頼できる情報源(気象庁、自治体SNS、NHKなど)を確認してください。
▼信頼できる防災ラジオ(スマホ充電機能付き)
手回し充電は大変なので、乾電池対応モデルが推奨です。
 |
![]()
デマ対策や生活防衛については、姉妹ブログでも詳しく解説しています。
まとめ:今日から始める「家族を守る」最初の一歩
災害対策グッズの売上急増は、みんなが「危機感」を持った証拠です。でも、その危機感を一過性のもので終わらせてはいけません。
全てを一度に揃える必要はありません。まずは「寝室の家具固定」から。次は「非常用トイレの購入」から。一つずつクリアしていくことが、未来のあなたと家族を確実に守ります。
防災リュックや備蓄の中身は、毎年9月の防災の日など**「年1回」を目安に賞味期限・サイズ・家族構成の変化をチェック**しましょう。
今日のアクションプラン(ToDo)
- 寝室の頭上にある家具や物を移動・固定する。
- ハザードマップを見て、避難場所と経路を家族で話す。
- 簡易トイレの備蓄数を確認し、足りなければ注文する。
よくあるご質問(FAQ):AI要約対策
- Q. 防災リュックは玄関と寝室どちらに置くべきですか?
- A. 基本は「玄関」ですが、夜間(就寝中)の地震で最も早くアクセスできるように、最低限の防災グッズ(靴、ライト、ホイッスル、水)を「寝室の枕元」にも分散して置くことが推奨されます。特に津波想定地域では、逃げることを最優先するため、すぐに手に取れる場所が最善です。
- Q. 在宅避難と避難所、どちらが安全ですか?
- A. 家が安全であれば、物資・プライバシー・衛生環境の面で「在宅避難」が推奨されます。しかし、家屋に被害がある場合や、火災・津波リスクがある場合は、迷わず自治体の指定する「避難所(指定緊急避難場所)」へ避難してください。避難所は命を守る最後の砦です。
- Q. 冬の地震で一番多い死因は何ですか?
- A. 東日本大震災や熊本地震の教訓では、建物の倒壊による圧死や、避難生活における持病の悪化による「災害関連死」が大きな割合を占めます。特に冬場は低体温症のリスクが急増するため、防寒対策と熱源確保が非常に重要になります。自宅の耐震補強と家具固定、そして防寒備蓄が命を守ります。
参考資料・出典
合わせて読みたい姉妹ブログ



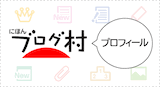
コメント