
在宅避難とは?必要物資と成功させる5つのポイント??
ご挨拶とこの記事の目的?
こんにちは、防災ブロガーのオウチックスです?。大規模災害が発生すると、避難所だけでなく「自宅にとどまる」選択肢があります。これが在宅避難。
内閣府は自宅の安全が確保できる世帯に対し、在宅避難を推奨し、その支援手順を自治体に示しています。
本記事では在宅避難の定義・メリット・リスクを整理し、必須の「食料・水・電気」を中心に、備えるべきアイテムと量を政府資料で裏付けしながら解説します。
※避難所生活のようすはこちら!
※これから起こり得る災害はこちら
? 目次
在宅避難とは??
地震・豪雨などで避難指示が出ても、自宅が倒壊・浸水・火災の恐れがない場合は、自宅にとどまり生活を継続する選択を指します。
内閣府の「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」では、「避難所での集団生活が困難/必要ない住民を支援対象に含める」と明記。
在宅避難が注目される背景
- 避難所の過密化を防ぎ、要配慮者スペースを確保できる。
- 感染症リスク・プライバシー問題を回避できる。
- ペットや介護者と離れずに済む。
メリットとデメリット⚖️
◆ メリット
- 自宅設備を活用でき、生活レベルを保ちやすい。
- 感染症クラスターや騒音ストレスを回避。
- ペット・要配慮家族と一緒に過ごせる。
◆ デメリット
- ライフライン断絶時、自力で水・食料・電気を確保しなければならない。
- 自治体によっては支援物資の配布が避難所優先で遅れる場合がある。
- 安否確認が遅れやすいので、在宅避難者登録や近隣ネットワークが不可欠。
必須3大物資:食料・水・電気???
① 食料:7日分×1,800kcal/日
経済産業省が示す災害時備蓄指針では、主食+副菜+嗜好品を組み合わせ、調理不要・長期保存が基本。
| 区分 | 例 | 1日目安量 |
|---|---|---|
| 主食 | アルファ化米・レトルトごはん | 2食 |
| 副菜 | 野菜スープ缶・ツナ缶 | 1〜2食 |
| 嗜好品 | ビスケット・チョコ | 適量 |
② 水:1人1日3L ×7日=21L
水は飲料用2L+調理・衛生1Lが目安。500mLペットボトルなら42本。
給水車利用を想定し、10L折りたたみタンクを1つ備蓄すると搬送が楽です。
③ 電気:発電能力200Wh/日
停電が7日続く想定でポータブル電源1,000Wh++ソーラーパネル200Wが推奨。
消費者庁はポータブル電源の事故防止ガイドで、屋外充電・通電火災対策を呼び掛けています。
太陽光発電はこちら!
+αで役立つ4カテゴリー?️
- 衛生:簡易トイレ35回分、ウェットティッシュ400枚、ゴミ袋30枚
- 情報:手回しラジオ+乾電池、モバイルWi‑Fiプリペイド
- 医療:常備薬1カ月分、消毒液、包帯・ガーゼ、体温計
- 安全:ヘルメット、厚手手袋、笛、防犯ブザー、現金1万円小分け
◆ ペット・乳幼児・高齢者は追加備蓄が必要
ペットフード7日分、紙おむつ・粉ミルク、介護食・お薬手帳のコピーなど、要配慮者ごとの専用物資を忘れずに。
備蓄計画とローリングストック術?
「備えたまま放置→賞味期限切れ」を防ぐにはローリングストックが最適。
買い物→収納→日常消費→足りない分を補充、の循環で常にフレッシュな備蓄を維持できます。
◆ 1カ月チェックリスト
- ペットボトル水は開封日をペンで記入し、古い順に消費。
- レトルトご飯は賞味期限3カ月前にカレーで消費→即補充。
- ポータブル電源は30日に1回20%→80%充放電でバッテリー劣化を防止。
FAQ
Q. 在宅避難でも支援物資は受け取れますか?
A. 受け取れますが登録制の自治体が多いです。平時に「在宅避難者登録」の方法を確認し、手順を家族で共有しておきましょう。
Q. 太陽光パネルが無い家庭はどうすれば?
A. ガソリン発電機も選択肢ですが、屋外設置・排ガス対策が必須。消費者庁は屋内使用によるCO中毒事故を警告しています。
Q. どこまで備えれば十分?
A. 国は3日分を推奨していましたが、近年の大型災害では7日以上ライフラインが止まる事例が増えています。家族構成と地域リスクを考慮し「7日+α」を目標にしましょう。
まとめ:自宅を災害対応拠点に✨
在宅避難は「避難所に行かない」というだけでなく、自宅をシェルター化する積極策です。
食料・水・電気の3大物資を7日分用意し、衛生・情報・医療・安全をプラスすれば、災害時でも家族の健康と尊厳を守れます。
今日からローリングストックを始め、我が家シェルター化計画を実践しましょう!
本記事には PR が含まれます
関連記事
? 参考文献(省庁資料)






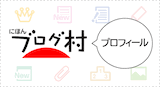
コメント