
再エネ賦課金が増える理由とは?自家発電しない人ほど損をする構造を解説
再エネ賦課金は今後も上昇が続くと予測されています。
電気料金を抑えるには「電力を買わない」選択肢=自家発電が有効です。
補助金制度の活用で初期費用の負担を軽減できる可能性もあります。
こんにちは、防災と電気代問題に詳しいオウチックスです?⚡
毎月の電気料金に含まれている「再エネ賦課金」、その金額が年々増えていることをご存じでしょうか?
この目に見えづらいコスト、実は再生可能エネルギーの普及を支える重要な制度である一方で、自家発電をしていない人ほど重くのしかかる構造になっています。
この記事では、再エネ賦課金がなぜ高くなっているのか、どんな人がどれだけ損をしているのか、そしてその対策としての「自家発電」や補助金制度を、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
この記事でわかること
- 再エネ賦課金が上がり続ける背景
- 自家発電が“自己防衛”になる理由
- 補助金の最新事情と損しない方法
再エネ賦課金が上がり続ける理由とは??
再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、国が太陽光や風力などの再生可能エネルギーを電力会社から一定価格で買い取る際に必要な費用を、私たち利用者が負担する仕組みです。
2012年に始まった「FIT制度(固定価格買取制度)」により、再エネ設備の導入が急拡大。その分、買い取りにかかる費用も増加し、それがそのまま賦課金として毎月の電気料金に上乗せされてきました。
実際、2025年度の再エネ賦課金単価は3.98円/kWh。たとえば月に400kWh使用する家庭なら、約1,592円の負担になります。
| 月間使用量 | 単価(2025年度) | 月額負担額 |
|---|---|---|
| 400kWh | 3.98円 | 約1,592円 |
| 600kWh | 3.98円 | 約2,388円 |
しかもこの負担は一時的なものではなく、2032年ごろまで続くと予測されています。その理由は、FIT制度によって買い取りが約束された期間(多くが20年契約)がまだ終わっていない案件が多いためです。
つまり、再エネの導入が増えれば増えるほど、それを支えるための賦課金も比例して膨らみ、私たちの電気代に跳ね返ってくる構造になっているのです。
自家発電が「負担回避」のカギ?
では、この再エネ賦課金の負担を減らすにはどうすれば良いのでしょうか?
答えは、「電力会社から買う電力量を減らす」ことです。
再エネ賦課金は、実際に購入した電力量に応じて計算されます。そのため、電気の使用量を減らすのではなく「購入量」を減らすことが、最も確実な回避策になります。
そこで注目されているのが家庭での自家発電です。たとえば太陽光パネルを屋根に設置すれば、日中の電力を自給できるため、電力会社からの購入量が減ります。
| 電力購入量 | 再エネ賦課金(3.98円/kWh) |
|---|---|
| 400kWh(通常) | 約1,592円 |
| 200kWh(太陽光併用) | 約796円 |
この差は約800円/月。年間にすれば9,600円、10年ではおよそ10万円の節約につながります。
つまり、自家発電は再エネ賦課金を合法的かつ確実に軽減できる唯一の方法とも言えるのです。
自家発電しない人に迫る“逆累進”の実態?
ここからが本記事の核心です。
再エネ賦課金は、ただ「使えば払う」という単純な仕組みではなく、自家発電をしているかどうかで大きな差が出る構造になっています。
というのも、賦課金の総額は全国的な「電力購入量」で按分されるため、太陽光パネルを導入して電力会社から電気を買わない家庭が増えると、その分、残りの人たちにより多くの負担がのしかかるからです。
この構造をわかりやすく整理すると、以下のようになります:
- ? 太陽光付きの戸建住宅:自家発電で購入電力量が少ない → 賦課金も少額
- ? 古い賃貸住宅や集合住宅:発電手段なし → フルに賦課金を負担
- ? 一部の企業:再エネ導入済で電力コスト圧縮 → 未導入企業にしわ寄せ
つまり、「発電できる人」が得をして、「できない人」が損をするという逆累進課税のような構造になっているのです。
これこそが、再エネ賦課金の“見えにくい不公平”であり、知っている人だけが回避できる損失とも言えます。
対策を講じた人と、何もしない人との間に、年々差が広がる時代──それが、いま進行しているエネルギー政策の現実です。
?「知らなかった」では済まされない時代に。
この仕組みを理解することで、あなたの家庭にもできる節約と備えが見えてきます。
補助金はここまで手厚くなっている!?
「太陽光発電は高くて手が出ない」と思っていませんか?
実は今、国や自治体による補助金制度が大幅に拡充されており、初期費用ゼロ円で導入できるプランも増えてきています。
まずは、代表的な補助制度を見てみましょう:
| 制度名 | 概要 | 補助額例 |
|---|---|---|
| 国のZEH補助金 | 高断熱・省エネ住宅への太陽光・蓄電池導入支援 | 最大100万円 |
| 自治体の太陽光補助 | 地域により設置費用を助成(市区町村単位) | 10〜30万円程度 |
| 蓄電池導入補助 | 災害時の備えとしてセット導入に対し優遇 | 最大60万円(条件あり) |
こうした補助に加え、以下のような「初期費用ゼロ円」で始められる導入方法も登場しています:
- ? リース契約型:電力会社が設備を無償設置し、電気料金に分割して返済
- ? 住宅ローン併用型:ZEH住宅建築時にローンに組み込み導入
- ? 簡易自家発電型:ポータブル電源+折りたたみソーラーパネルで手軽に発電
このように、資金的なハードルで諦めていた人にも、現実的な選択肢が広がってきているのが今のトレンドです。
補助制度の内容は地域によって異なるため、まずは「お住まいの自治体名 + 太陽光 補助金」などで検索してみると良いでしょう。
やらないのはもう自己責任?その判断基準とは?♂️
ここまで読み進めてくださった方は、すでにお気づきかもしれません。
✔ 再エネ賦課金は年々上昇
✔ 自家発電をすれば合法的に軽減可能
✔ 補助金制度で導入コストも下がっている
それでも「何も対策せず、高くなった電気代に文句を言う」だけでは、損する側に回り続ける可能性があります。
もちろん、賃貸に住んでいる方やローンへの不安がある方など、すぐに導入できない事情がある場合も多いでしょう。
しかし、だからといって何もできないわけではありません。以下のような「行動の選択肢」は、誰にでもあるはずです:
- ⏳ 賃貸世帯向けの減免制度や自治体による一部助成の確認
- ⚡ 電力会社の見直し・再エネ比率の高いプランへの乗り換え
- ? ベランダ設置型のミニソーラー+ポータブル電源の活用
知っているのに動かないのか、知ったからこそ一歩踏み出すのか。
この違いが、将来の電気代やエネルギーの自立性に大きな影響を与える時代になってきているのです。
その選択は、あなたの生活と未来に直結します。
まとめ|行動する人だけが損しない時代へ?♂️
再エネ賦課金は、日本の再生可能エネルギーを支える大切な制度です。
しかし、電力会社からの購入量に応じて負担が決まる以上、対策を取った人とそうでない人との間に“電気代格差”が生まれるのも事実です。
✔ 自家発電による賦課金負担の軽減
✔ 補助金制度やゼロ円導入プランの活用
✔ 電力会社やプランの見直し、ミニソーラー活用
今後、さらに高くなるとされる電気代に備え、あなたの生活に合った防衛策を検討してみてはいかがでしょうか。
「再エネの理念には共感する。でも、何もしないままでは損をする」──そんなあなたにこそ、この記事が役立てば嬉しいです。
※本記事には PR が含まれます
? 参考URL
❓ よくある質問(FAQ)
自家発電をすれば再エネ賦課金は完全にゼロになりますか?
完全なオフグリッド生活でない限り、電力会社から購入した分には賦課金がかかります。ただし、自家発電によって購入量を減らせば負担を大きく軽減できます。
賃貸でも再エネ対策はできますか?
はい、ベランダ設置型のソーラーパネルやポータブル電源との組み合わせにより、賃貸でも自家発電の選択肢があります。大家さんの了承と自治体の補助金を確認しましょう。
補助金の申請はどこから行えますか?
自治体の公式ホームページや資源エネルギー庁、環境省の補助金ポータルなどから申請案内を確認できます。
$
$$$$$$


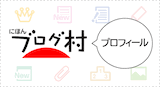
コメント