
※本記事はPRを含みます
在宅避難のすすめ2025|避難所の現実と「我が家シェルター計画」

クロマル:避難所に行けば安心にゃ?実はそうじゃないにゃ。収容制限や衛生問題、ペットの制約など現実は厳しいにゃ。在宅避難で命を守る方法、しっかり学ぶにゃ!
災害発生時に多くの人が向かう「避難所」。しかし、その実態は決して理想的な避難空間ではありません。2024年以降の各地調査によれば、避難所の定員超過、感染症リスク、トイレ不足、プライバシーの欠如など、さまざまな問題が浮き彫りになっています。
こうした現状から、注目されているのが「在宅避難」です。安全な自宅でライフラインを確保しながら避難生活を送る選択肢が、都市部を中心に広がりを見せています。
この記事では、避難所の課題を明らかにしつつ、在宅避難を成功させるための備えと戦略を、実例・制度・アイテム・ネットワークの観点から網羅的に解説します。
避難所生活のリアル|5つの過酷な現実

クロマル:「避難所に行けば安心」はもう古い考えにゃ。現実は、定員オーバーや感染症、ストレスや防犯の問題が山積みにゃ。ここで5つのリスクを具体的に紹介するにゃ!
① 定員オーバーによる入所制限
大規模災害発生時、避難所には想定を大きく上回る避難希望者が殺到します。たとえば東京都内のある区では、想定8,000人に対して14,000人以上が集まり、発災当日に入所制限がかかった事例も。入れなかった人は車中泊や路上泊を強いられ、寒暖差による低体温症が続出しました。
② トイレ・衛生環境の深刻な悪化
発災直後は水道の停止によりトイレが使えなくなり、仮設トイレの設置も72時間以上かかることが多いです。悪臭や汚物が放置される中でノロウイルスやインフルエンザの感染が広がり、吐瀉物の処理も間に合わず衛生崩壊が一気に進行します。
③ エコノミークラス症候群と感染リスク
硬い床で寝る避難所では、体を動かさずに長時間過ごすことで足の血流が悪くなり血栓ができるリスクが高まります。さらに密閉された空間では飛沫感染のリスクも高く、クラスター発生の温床となります。
④ メンタルの限界と防犯不安
避難所の多くは照明がつけっぱなしで、プライバシーがありません。睡眠不足やストレスから怒号や家庭内暴力、性被害の発生率が上昇し、女性や子ども、高齢者にとって非常に不安な空間となります。「安全」と「安心」は別物です。
⑤ ペットと一緒にいられない現実
動物アレルギーや鳴き声、においへの配慮から原則としてペットは避難所同室不可となっている地域が多く、「同行避難」はできても「同伴避難」は認められません。結果として屋外にケージを置くか、車中で過ごすこととなり、飼い主が血栓症になるケースも報告されています。
在宅避難に必要な3つの備え|命をつなぐ水・食料・電気

クロマル:「我が家で避難」は安全な家とライフラインの備えが前提にゃ!水・食料・電気、この3つがそろえば家が最強の避難所になるにゃ!しっかり準備していこうにゃ!
1. 水の備蓄|1人あたり21Lが基本
在宅避難を成功させるには、1人1日3L × 7日分=21Lの水を確保することが推奨されています。500mLボトルの小分けのほうが使いやすく、回転(ローリングストック)しやすいです。
また、給水車対応のために10Lの折りたたみタンクも用意しておくと安心です。
2. 食料の備蓄|加熱不要・水不要がカギ
最低7日分、可能なら10日分以上の非常食を備えましょう。調理不要で水も使わずに食べられるもの(アルファ化米、缶詰、栄養バーなど)を組み合わせて用意します。
3. 電気の備え|発電+蓄電で生活維持
停電の長期化に備え、太陽光+ポータブル電源の組み合わせが有効です。スマホや照明に加え、小型冷蔵庫なども活用できます。
- ポータブル電源:容量1,000Wh以上
- ソーラーパネル:折りたたみ式200W
- LEDランタン:乾電池式+USB充電式
在宅避難における制度と支援格差|行政支援を受けるには?

クロマル:在宅避難って自己責任って思ってないかにゃ?でも実は、ちゃんと自治体に登録すれば支援が受けられるにゃ!放置してると支援格差に泣くことになるから、準備は忘れずにゃ!
■ 在宅避難者登録制度とは?
自治体の多くでは、地震や水害などで避難所へ行かずに自宅で避難する人のために、「在宅避難者登録制度」を用意しています。
登録をすることで以下のような支援を受けることが可能になります:
- 物資の配布(飲料水・食料・生活必需品など)
- 健康チェックや安否確認の訪問対象に含まれる
- 自治体からの支援や連絡が届きやすくなる
災害発生前に登録できる自治体も増えており、日頃から確認・準備しておくことが大切です。
■ なぜ支援格差が生まれるのか
物資配布や支援は「避難所中心」で動くため、在宅避難者は後回しになりやすいのが現実です。
特に支援物資が限られる発災初期には「避難所にいない人には配れない」という事態が起きます。これが「支援格差」です。
さらに、在宅避難者は孤立のリスクも高まります。以下のようなケースが想定されます:
- 安否確認がされない(住民票に基づく戸別訪問も限界)
- 高齢者・持病持ちの世帯が支援から漏れる
- 正確な情報が届かず、配布時間や場所を知らない
■ 登録の確認と家族の共有を
お住まいの自治体の「在宅避難者登録制度」があるかを区役所・市役所の防災担当課に確認し、登録方法・対象者・物資配布の流れを把握しておきましょう。
また、家族内で以下を共有しておくと安心です:
- 登録状況(どこに・いつ・誰の名前で)
- 物資配布拠点の場所とアクセス手段
- 災害時に確認すべき公式SNSやラジオ放送
共助ネットワークと地域連携|孤立しない仕組みをつくる

クロマル:ひとりじゃ限界があるにゃ。ご近所とゆるやかに助け合えば、支援が届かない時でも安心にゃ!LINEや自治会、物々交換も大切な命綱になるにゃ!
■ 「ご近所力」で命をつなぐ
在宅避難の成功は「我が家の備え」だけでなく、地域のつながり=共助にも左右されます。支援が遅れる状況では、自助と共助で9割をカバーする意識が重要です。
以下のような共助行動が、いざという時に役立ちます:
- 普段から近所と顔を合わせておく
- 在宅避難者同士で「声かけ合い・確認し合い」
- 情報が届きにくい高齢者世帯をフォロー
■ 今すぐできる「ゆるネットワーク」づくり
自治会に入っていなくても、できることはあります:
- LINEのオープンチャットで町内グループを作成
- 余った備蓄品の交換(水・カセットボンベなど)
- 共有充電所の設置(自治会やマンション管理組合など)
災害時に閉鎖的にならず、「助け合える雰囲気づくり」が命を救います。
■ 共助×備え=レジリエンスの鍵
災害時、行政による支援(公助)は全体の1割未満に留まります。「自助7:共助2:公助1」が現実のバランスです。
この比率を理解し、「自宅+近隣支え合い」で最低7日間の持ちこたえ力を確保することが、地域全体の生存率を高める鍵です。
まとめ|在宅避難で守る命と暮らし

クロマル:避難所がダメってわけじゃないにゃ。でも、住める家があれば、在宅避難ってすごく強い選択肢になるにゃ。今から「自宅をシェルター化」する備えを始めるにゃ!
避難所は命をつなぐ最終手段ですが、人口密集地では環境が過酷で、ペットや高齢者、持病を持つ方が安心して過ごせるとは限りません。
だからこそ、自宅が安全なら在宅避難を第一選択肢にできる備えが求められます。
以下の3つを押さえて、我が家を最強の避難所にしましょう:
- 7日分の水・食料・電気の確保
- 家具固定・家屋の安全対策
- 在宅避難者登録とご近所ネットワーク
参考リンク
FAQ(よくある質問)
Q. 自宅が半壊でも在宅避難できますか?
A. 倒壊や浸水リスクがないか専門家の判断を待ちましょう。危険な場合は避難所を優先してください。
Q. 在宅避難者は物資をもらえないの?
A. 事前に登録することで支援対象になります。災害前の登録確認がカギです。
Q. ペットと一緒に在宅避難できますか?
A. 自宅が安全なら可能です。車中や屋外テントの場合は暑さ・寒さ対策を忘れずに。
※本記事はPRを含みます







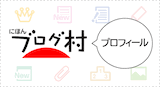
コメント