

クロマル:「水と食料はバッチリ!」って安心してるそこのあなた、ちょっと待つにゃ!
実は災害時、一番困るのは「食べるもの」じゃなくて「出すところ」なんだにゃ。
能登半島地震の教訓から、これまでの常識だった「3日分」じゃ全然足りないことが分かってきたにゃ。
今回は、マンション住まいの人が絶対に知っておくべき排水管のリスクと、自宅を地獄のような悪臭から守るための「14日分備蓄」の正解を教えるにゃ!
✅ この記事でわかること(&解決する未来)
- なぜ「水」より先に「トイレ」を備えるべきなのか?(命に関わる理由)
- マンションで地震直後にトイレを流すとどうなるか?(汚水逆流の恐怖)
- 4人家族なら「280回分」必要!最新の備蓄計算式とゴミ問題
- 絶対に臭わせない「最強の簡易トイレ」3選(BOS・トイレの女神・Qbit)
- マンホールトイレと携帯トイレの違いとは?

クロマル:まずは「トイレなんて後回しでいい」という勘違いを捨てるにゃ。命と尊厳に関わる怖い話をするにゃ。
なぜ「水・食料」より「トイレ」が最優先なのか?
大地震が起きたとき、多くの人はまず「水の確保」や「食料の備蓄」を心配します。しかし、被災経験者が口を揃えて「最も辛かった」「もっと備えておけばよかった」と語るのは、実は「トイレ」なのです。
人間は食事を数日我慢することはできても、排泄を我慢することはできません。災害用トイレの備えがないことは、単に不便なだけでなく、生命維持そのものを脅かすリスクとなります。
【能登の教訓】仮設トイレは「すぐに来ない」現実
「いざとなったら避難所に行けば仮設トイレがある」と思っていませんか?その認識は、2024年の能登半島地震で完全に覆されました。
NPO法人日本トイレ研究所が2024年6月に発表した調査データによると、避難所のトイレ環境の実態は以下の通りでした。
出典:NPO法人日本トイレ研究所 調査データ(設置日が判明した避難所10箇所の集計)より作成
このデータが示す通り、半数以上の避難所ではトイレの設置に4日以上かかり、3割の場所では1週間以上待たされています。
半島特有の道路寸断、積雪による交通麻痺により、プッシュ型支援物資の到着は大幅に遅れました。もし自宅にトイレの備えがなければ、あなたは発災直後から1週間以上、排泄できる場所を失うことになります。
排泄を我慢すると「死」を招く(災害関連死の真実)
トイレ環境の悪化は、直接的に命を奪う原因となります。これを「災害関連死」と呼びます。
内閣府の定義では、以下のように定められています。
「災害による負傷の悪化、または避難生活における身体的負担による疾病により死亡したもの(災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害との相当の因果関係があると認められたもの)」
- トイレが汚い・臭い・行列ができるため、「トイレに行きたくない」と考える。
- トイレの回数を減らすために、「水や食事を控える」ようになる。
- 脱水症状になり、血液がドロドロになる。
- 狭い避難所や車中泊で動かないため、脚に血栓ができる(深部静脈血栓症)。
- 血栓が血流に乗って肺に飛び、血管を詰まらせる「エコノミークラス症候群(肺塞栓症)」を発症し、呼吸困難や死に至る。
※日本呼吸器学会や厚生労働省の予防指針に基づくメカニズムです。
2016年の熊本地震では、災害関連死(208名)の多くが呼吸器・循環器系の疾患であり、トイレ我慢による水分制限が遠因となったと指摘されています。トイレを備えることは、衛生の問題ではなく、生存のための防衛策なのです。
マンション住民への警告!「流す」は加害行為になる
マンションやアパートにお住まいの方は、特に注意が必要です。地震直後、「断水していないから」といって、いつものようにトイレを流してはいけません。
目に見えない場所(壁の中や床下)で排水管が破損したり、継ぎ目が外れていたりする可能性があります。その状態で上の階の人が水を流すとどうなるでしょうか。
行き場を失った大量の汚水と圧縮された空気が、下の階(特に1階や2階)のトイレや風呂場の排水口から「噴水のように」逆流・噴出する恐れがあります。
⚠️ 国土交通省ガイドラインの警告
国交省の「マンホールトイレ整備ガイドライン」等でも、「排水設備の安全が確認されるまでは、トイレの使用(排水)を禁止する」ことが強く推奨されています。
確認せずに流す行為は、階下の住居を汚物まみれにし、損害賠償問題にも発展しかねない「加害行為」です。管理組合からの「使用許可」が出るまでは、絶対に簡易トイレを使ってください。

クロマル:「じゃあ何個買えばいいの?」って思うよにゃ。ここ重要だにゃ。3日分じゃ全然足りない計算式を見せるにゃ。
備蓄量の新常識:4人家族なら「280回分」が必要な理由
これまでの防災ガイドでは「最低3日分、できれば7日分」と言われてきました。しかし、物流が長期停止する現代の大規模災害において、3日分では圧倒的に不足します。
「3日分」ではゴミの山に埋もれる
トイレ備蓄で最大の盲点になりがちなのが、「使用済み汚物のゴミ回収」です。
災害時、トイレが使えない状況では、当然ゴミ収集車(パッカー車)も来ません。道路の啓開が遅れれば、ゴミ収集の再開はさらに後回しになります。
能登半島地震では、し尿処理施設の停止や道路状況の悪化により、バキュームカーの回収再開に時間を要しました。実際、2024年1月23日時点で県内の一部し尿処理施設が長期停止しているという報告も上がっており、回収再開に3週間以上かかった地域もありました。
もし3日分しか備蓄がなければ、4日目以降は排泄する手段がなくなり、さらに最初の3日分の汚物が放つ悪臭と戦いながら、残り10日間以上を耐えなければなりません。
【計算式】最低7日、目指せ14日!
物流停止とゴミ回収停止のリスクを考慮した、2025年版の新しい備蓄基準は以下の通りです。
? 災害用トイレ必要数の計算式
1人1日5回 × 家族人数 × 14日分
| 家族人数 | 14日分の必要数 (推奨) |
7日分の必要数 (最低ライン) |
|---|---|---|
| 1人 | 70回分 | 35回分 |
| 2人 | 140回分 | 70回分 |
| 3人 | 210回分 | 105回分 |
| 4人 | 280回分 | 140回分 |
「えっ、280回分も!?」と驚かれるかもしれません。しかし、これは決して大げさな数字ではありません。1日5回というのは最低限の回数であり、冬場や体調不良時はもっと増える可能性があります。
なぜ「防臭」が必要なのか?臭いの正体
280回分の汚物は、凝固剤で固めたとしても約80kg〜110kgもの重量になります。これを2週間、自宅に保管しなければなりません。
排泄物の臭いの主成分は「スカトール」や「インドール」といった物質です。これらは非常に強力な悪臭を放ち、一般的なポリ袋(ポリエチレン)の分子の隙間をすり抜けてしまいます。
だからこそ、単に袋があればいいのではなく、ガスバリア性の高い「防臭袋」が必須となるのです。
災害用トイレの種類:携帯トイレ vs マンホールトイレ
ここで、言葉の整理をしておきましょう。災害用トイレには主に2つの種類があります。
1. 携帯トイレ(簡易トイレ)
今回おすすめしているのがこちらです。
自宅の洋式トイレに袋を被せて使用するタイプです。「凝固剤」と「汚物袋」がセットになっています。水を使わず、可燃ごみとして処理できるのが特徴です。マンション等の「在宅避難」ではこれが主力になります。
2. マンホールトイレ
避難所やマンションの敷地内にあるマンホールの蓋を開け、その上に便座とテントを設置して使用するタイプです。下水道管に直結するため、汚物を溜め込まずに流せますが、下水道本管や処理場が被災していると使えません。
また、設置や使用開始には、下水道管の被災状況を確認するなど専門家による事前判断が必要不可欠です。そのため、発災直後すぐに使えるとは限りません。

クロマル:普通のゴミ袋じゃ臭いは防げないにゃ。ここからは、プロも認める「絶対に臭わせない」最強トイレを紹介するにゃ。
絶対に臭わせない!最強の簡易トイレ3選【2025年版比較】
市販の「黒いポリ袋」だけでは、悪臭成分の分子が袋を通り抜けてしまい、部屋中に臭いが充満します。
自宅避難を成功させるには、医療レベルの防臭技術を使った製品や、長期保存に特化した製品を選ぶ必要があります。
| 製品名 | 1回あたり | 特徴 | おすすめユーザー |
|---|---|---|---|
| 驚異の防臭袋BOS | 約85円~ | 医療用技術で圧倒的な防臭力。絶対に臭わせたくないならコレ一択。 | 臭いに敏感な人 マンション住まい |
| トイレの女神 PREMIUM | 約75円~ | 15年保存可能。日本製。アルミパッケージで劣化しにくい。 | 長期備蓄したい人 入れ替えが面倒な人 |
| Qbit(キュービット) | 約60円~ | 1回約60円と高コスパ。凝固剤が大容量(10g)で安心。 | 大量備蓄したい人 大家族 |
※価格は2025年11月時点のAmazon等実売価格であり、変動する可能性があります。最新の価格や在庫状況は各リンク先でご確認ください。
【防臭力の王様】驚異の防臭袋BOS(ボス)非常用トイレセット
医療現場で「オストメイト(人工肛門)」の処理袋としても使われている、圧倒的なガスバリア性(防臭性能)を持つ「BOS」を採用したセットです。
実験では、カレー粉や生ゴミを入れても全く臭いが漏れないほどの性能を持っています。価格は少し高めですが、「2週間ゴミを捨てられない」という極限状況において、精神的な安定を買えると思えば、決して高い投資ではありません。
 |
【うんちが臭わない袋】 BOS非常用トイレ (Bセット) 50回分 災害/携帯/簡易トイレ/防災グッズ/15年保存 ◆防臭 防菌◆ 臭わない袋BOS付き |
![]()
【長期保存の安心】トイレの女神 PREMIUM
防災グッズで困るのが「使用期限の管理」です。多くの簡易トイレは使用期限が10年程度ですが、この製品は「15年保存」を謳っています。
その秘密は、凝固剤を「アルミパッケージ」で個包装している点にあります。湿気や光による劣化を防ぎ、いざという時に「固まらない」というトラブルを防ぎます。すべて日本製の安心感も魅力です。
 |
![]()
【コスパ最強】Qbit(キュービット)
「280回分も揃えるとなると、費用が…」という方にはこちら。1回あたり約60円という高いコストパフォーマンスを実現しています。
安さだけでなく、凝固剤の量が一般的製品よりも多い(10g以上)ため、尿量が多い場合でもしっかり固まります。他社製品は7g程度のものが多く、量が多いと固まりきらないことがありますが、Qbitなら安心です。手袋付きモデルもあり、衛生面への配慮も十分です。
 |
![]()

クロマル:「新聞紙で代用できる」なんて噂を信じちゃダメだにゃ。それは数時間だけの緊急措置だにゃ。
やってはいけない「自作トイレ」の落とし穴
ネット上には「新聞紙や猫砂で簡易トイレは自作できる」という情報がありますが、これらはあくまで「凝固剤が尽きてしまった時の最終手段」と考えてください。
新聞紙と猫砂は「あくまで緊急用」
新聞紙には吸水性はありますが、水分をゼリー状に固める「保水力」はありません。圧力がかかれば汚水が染み出します(逆戻り)。
また、猫砂は吸水・消臭効果がありますが、人間の尿量(1回200〜400ml)に対しては量が足りないことが多く、抗菌作用も人間用には設計されていません。放置すると菌が爆発的に増殖します。
何より、猫砂は水分を吸うと非常に重くなります。ゴミ出しの際、高齢者では持ち運べない重さになってしまうリスクや、自治体によっては「汚物を吸った猫砂」の回収を拒否するケースもあります。
ゴミ袋(ポリ袋)は臭いを通す
スーパーの袋や家庭用のゴミ袋(ポリエチレン製)には、目に見えない微細な隙間があります。水分は通しませんが、悪臭の分子(ガス)はこの隙間を通り抜けてしまいます。
自作トイレを室内に保管すると、数時間で部屋中がトイレの臭いになり、生活できなくなります。長期戦が見込まれる災害時こそ、専用の「防臭袋」と「抗菌凝固剤」が必須なのです。
【実践編】実際に自宅トイレに設置する手順
商品が届いたら、必ず一度「予行演習」をしてください。いざという時に慌てないための手順です。
- 便座を上げる:まずは便座を上げます。
- 下地袋をセット:45Lのゴミ袋を便器全体に被せます(水に濡れないように)。
- 便座を下ろす:その上から便座を下ろします。
- 排便袋をセット:便座の上から、凝固剤セットに入っている「排便袋(黒い袋など)」を被せます。
- 用を足す:この状態で用を足します。
- 凝固剤を入れる:使用後すぐに凝固剤を振りかけ、固まるのを待ちます。
- 袋を取り出し縛る:排便袋を取り出し、空気を抜いて口を固く縛ります。
- 防臭袋に入れる:最後にBOSなどの「防臭袋」に入れ、口をねじって結べば完了です。
まとめ:トイレの備えは「家族の尊厳」を守ること

クロマル:最後まで読んでくれてありがとだにゃ!トイレの備えがないと、恥ずかしくて辛い思いをするのは自分や家族だにゃ。
災害時のトイレ問題は、単なる衛生の問題を超え、人間の「尊厳」に関わる重大なテーマです。能登半島地震の教訓は、「公的な支援はすぐには来ない」「自分の排泄物は自分で守り切るしかない」という厳しい現実を私たちに突きつけました。
【今日からのアクション】
- 今すぐ「家族の人数 × 14日分(280回分)」を計算する。
- BOSやトイレの女神などの「防臭袋付きセット」を購入する。
- 商品が届いたら、週末に一度、家族で家のトイレにセットしてみる(予行演習)。
水や食料よりも先に、まずはトイレの備えを完璧にしてください。それが、災害時でも家族が笑顔で過ごすための第一歩です。



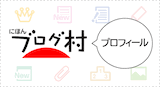
コメント